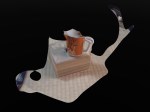先日、ヨメさんが見つけてくれた本のデザイン・出版に関するセミナーに参加し、大阪の出版社「松本工房」代表、松本久木氏の稀有な活動に触れることができました。尼崎のピッコロシアター閲覧室というこぢんまりとした空間で、20名ほどの参加者を前に繰り広げられた1時間半は、まさに目から鱗の連続。
「一人出版社」として追求する本の可能性
松本氏はご実家が演劇に関わっていたことから、芸術分野の書籍制作・出版をされています。驚くべきは、企画から編集、校正、ブックデザイン、製本手配、宣伝販売、さらには関連アイテムの制作や販路開拓まで、出版に関わるほぼ全ての工程をお一人でこなされている点です。
しかし、心を奪われたのは、その制作工程以上に「本の装丁」そのものでした。単に表紙が美しい、デザインが変わっているというレベルではなく、松本氏が手掛ける本は、「本」の作り方そのものから徹底的に練り上げられています。使う紙の種類、綴じ方、装丁方法、カバーの素材など、あらゆる製本技術の中から、内容や作家に最もふさわしいカタチを熟考し、緻密かつ大胆なブックデザインへと昇華されているのです。その並々ならぬこだわりは、造本装幀コンクールでの受賞実績にも表れています。
作品への深い敬意が息づくブックデザイン
セミナーでは、4名の演劇演出家の戯曲や記録、日記を書籍化した事例が紹介されました。松本氏は、それらの原稿のほぼ全てを読み込み、その内容に合った本のイメージを具現化することに心血を注がれています。
例えば、粗野なイメージの作品にはあえて背表紙のない製本を施したり、捉えどころのない作品では淡いグラデーションの中に目を凝らさないと読めないような題字を配したり。ペンネームに「銃」の字を持つ作家の本では表紙に穴を開け、フランス思想を感じさせる作家にはフランス装という伝統的な装丁方法を用いるなど、その発想は多岐にわたります。シリーズものでは、全体を見通して初めて一つのデザインが完成するような仕掛けや、言われなければ気づかないような細やかな工夫が随所に凝らされています。
実際に現物を見ると、素人目には採算が取れるのかと疑うほど凝った作りばかりで、製本工場から「これは無理」と断られることも少なくないとか。アートやデザイン系の書籍、絵本などでは珍しい装丁を見る機会はありますが、独りよがりで無く、商業ベースに乗せることを前提にしているのが驚きです。
クライアントの期待を超える「本」の創造
松本工房の書籍は、それぞれに書籍化を望むクライアントが存在することで成り立っているとのことです。しかし、出来上がった本はクライアントの期待をはるかに超えるものばかり。自費出版とは異なり、ビジネスとしての成立も目指されています。
「楽ではないが、一人だからこそできる」という松本氏の言葉の裏には、計り知れない労力があることでしょう。今回紹介の書籍は劇作家の作品といった特殊な分野ですが、作家や作品への深い敬意を持って唯一無二の形を創り出すその姿勢は、もはや「出版社」というよりも「本づくり作家」と呼ぶのがふさわしいと感じました。
松本氏がされている本の装丁は、まるで、クライアントから終の棲家(ついのすみか)を頼まれた建築家が、その思いを定着させるための最適な器のように、「本のカタチ」を探る作業にも感じられます。
目の前で「べらぼう」を見たかのような気がします。もの作りに向かう姿勢を正された機会になりました。
*仮フランス装 : 元々書籍の装丁を家人の好みで揃えるため、ブックカバーを手作りしていたフランスの文化から始まったスタイルだそうです。本来、手折りでするものを「フランス装」と呼び、機械で疑似的なスタイルにしたものを「仮フランス装」と呼ぶそうです。